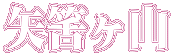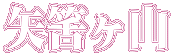BACK 擬宝珠山・象山
2008年11月14日
今日はこれから矢筈ヶ山に登るのだ。車を走らせて行くと、地蔵峠の付近から大山・矢筈山・甲ヶ山・船上山の稜線が一望することができた。これを縦走したら楽しいだろうなと思ってしまう。(実際可能なのだが、私には車があるので無理なのだ)
登山口の一向平キャンプ場に着いたのは10時20分である。管理棟で登山届けを出して歩き始めた。
大休峠までは中国自然歩道を行くので、整備された遊歩道が続いている。そのためか、けっこう家族連れが歩いていて、彼らは大山滝を見に行くのだ。(でも、登山口から大山滝までの遊歩道は最近崩落したらしくて、新しい道がつけられたのだ。この道はすごい遠回りで、しかもアップダウンが激しい。)
キャンプ場からは広い道を緩やかに上って行く。10分ほど行くと、階段のすごい下りがあった。そのあとしばらく平坦な道を行くが、再び階段の急下降、これは長かった。どんどん下って行く。この階段の下りからは紅葉がすばらしくきれいであった。
下りきったところが吊り橋の前であった。
長い吊り橋を渡ってから左に緩やかに上るとすぐに指導標がある。右に下ると「鮎返りの滝」があるというのだが、私はまっすぐに大山滝を目指す。(帰りに寄ろうと思っていたが、帰りにはすっかり忘れていた)
ここから少し行くと檜の林の中に「旦那小屋跡」があった。
檜林を抜けるとすばらしい紅葉の中を歩くようになった。つい、立ち止まって写真を撮ってしまうのだ。
小さな沢を渡ると登りになって、鮮やかな紅葉を眺めながら歩いて行くと檜林の平坦地になる。ここには木地屋敷跡の標識がたっていて、標識の後ろに石垣のようなものが見えた。こんな山の中に小屋や屋敷跡があるのはすごく不思議である。
檜林から階段を上がって行くと石地蔵がたっていた。石地蔵の先は檜林の平坦地で、すぐに大山滝の説明板があった。その先にベンチがあって休憩できるようになっている。滝にはどうして行くんだと見回すと、このベンチの広場の左に階段があった。
石段を少し下ると滝の展望台であった。ここからは二段になって流れ落ちる大山滝を眺めることができるのだ。落差42mの堂々とした滝である。今は二段の滝なのだが昔は三段の滝だったらしい。昭和9年の室戸台風で崩落して今のような二段の滝になってしまったのだという。
登山道に引き返して先を急ぐ。滝から先は鮮やかな紅葉で、大満足の道である。滝から8分ほど登ったところに「謎の石碑」という指導標があった。登山道から左に少し下るとその石碑がたっている。漢字が刻まれているのだが、昔、大山道の修繕に携わったひとの碑文らしい。
鮮やかな紅葉を眺めながら行くと、急な登りがあって、その先は檜林に入った。
林の中を少し行くと、地獄谷との分岐を示す指導標がたっていた。ここから目指す大休峠までは2.4kmである。
紅葉の中をジグザグに急登して尾根に出る。痩せた尾根の左右は開けていて、紅葉の山々を眺めることができる。すばらしくきれいだ。
紅葉の写真を撮りながら登って行って、三本杉別れに着いたのは12時10分であった。登山口から1時間50分たっている。ここから大休峠までは1.3kmである。
この先は山腹をトラバースする平坦な道なのだが、だいぶ疲れてきていて息が切れる。階段を上ってようやく峠を越えたが、そこは大休峠ではなかった。がっかりした。
さらにトラバース道を5分ほど歩くと、大休峠まで600mの指導標がたっていた。まだ600mもあるのかと思ってしまった。
緩やかなアップダウンの道を行く。左には大山が見える。
ようやく行く手に小屋が見えてきて、大休峠に着いたのは12時40分であった。
小屋の前のベンチで休憩する。なんか疲れ果てたという感じで、ここでコーヒーを飲みながらパンをかじった。朝から食べていないので、疲れは空腹だったからかもしれない。
小屋からは中国自然歩道を離れて、矢筈ヶ山への登山道に入る。笹藪の中の道を登ると傾斜が緩やかになって、そこから少し下るところから、すごい三角峰が目の前に聳えていた。これが矢筈ヶ山か、とんでもない登りになりそうだ…と、ため息が出てしまった。(でも、この山は前衛峰で山頂はこの奥に聳えているのだ)
ブナ原生林の中のすさまじい登りが始まる。山の急斜面を斜めに登ってゆくのだが、きつさは直登とかわらない。岩がゴツゴツする急斜面を必死で登って行く。ようやく傾斜が緩やかになって、山頂かと思ったら、さらにその奥に高く聳える緑の山が見える。これが本当の山頂であった。
ブナ林の稜線を緩やかに下るように歩いて行くのだが、ブナの古木がいろんな姿でたっていて、つい写真を撮ってしまう。
鞍部からは緩やかな登りになる。でも、すぐに傾斜はきつくなって、笹原の中に一直線につけられた道を急登する。
ようやく傾斜が緩くなると、右にカーブするように歩いて山頂に着く。山頂に着いたのは13時35分であった。疲れた。
山頂からは甲ヶ山の岩峰がすごい。でも、その右下に鋭い岩峰が見える。これが小矢筈ヶ山であった。すごい山である。これは登っておかなければいけない。
ザックを山頂に置いて、ステッキだけを持って小矢筈ヶ山に向かった。山頂からは急な下りである。どんどん下って行く。ようやく鞍部に着くと、そこから見上げる小矢筈は針のように鋭い岩山であった。この山にどうしたら登れるんだと思ってしまうほどの険しさである。
これは両手フル稼働で、なにかにつかまって登らなければいけないので、ステッキは鞍部において行くことにした。
ここからはただ目の前の岩場を必死で越えて行くだけであった。山頂直下にはすごいスラブがあって、これをどうして登るんだと思ったりしたが、木や岩につかまってようやく越えた。ピークに飛び出して山頂だと思ったらそうではなかった。そこから10mほど痩せた岩尾根を歩いてようやく山頂に着くのだ。
山頂はすごく狭くて、しかもどちらも断崖絶壁である。足が震えてしまう。小矢筈と書いた小さな木の札が灌木にくくりつけられていたので、この前で記念写真を撮った。
目の前に大きく聳える甲ヶ山はすごい迫力である。でも、眺めているうちに雲が湧いてきて、隠れてしまった。
あとは下らなければいけない。岩場の下りは本当に怖かった。すさまじい岩場を、三点確保、三点確保と自分に言い聞かせながら慎重に下った。ようやく鞍部にたどり着いたときはほっとした。
急な道を登って矢筈ヶ山の山頂にもどったら、夫婦連れの登山者が休んでいた。
ともかく小矢筈にも登ったので、ゆっくりと休憩することにする。この山頂にある三角点は一等三角点なのだ。山頂からは大山を眺めることができるのだが、逆光でしかも雲もわいてきて、きれいに展望することはできない。でも、甲ヶ山の雲は晴れていた。
十分景色を楽しんでから下山した。
来た道を戻るだけなので気はラクなのだが、時間が遅くなってしまった。大休峠への急下降は、気は急くのだが慎重に下って、峠からは急ぎ足で歩いて行く。このころには空が雲におおわれてしまって、紅葉もあまり鮮やかではない。
走るように下って、大山滝に戻ったのは15時35分、さらに急ぎ足で下って、登山口に戻ったのは16時15分であった。疲れた。
NEXT 船上山
BACK 私の山陽山陰の山百選
|
|

キャンプ場から遊歩道を行く

すごく急な階段を下る

吊り橋を渡る

旦那小屋跡

階段の登りになった

大山滝

地獄谷分岐

三本杉分かれ

大休峠

ブナ林を急登する

矢筈ヶ山山頂

小矢筈への登り

小矢筈の山頂
|